6. ページの構成(空白ページの処理)
電子書籍と紙の本の作成で目に見える一番の違いがこれですね。
たとえば、紙の本をめくると、表紙裏の見返しに文字が印刷されていないページが含まれていたりしますよね。
遊び紙と呼ばれたりしていますが、紙質によっては本にある種の雰囲気を生じさせ高級感をもたせる重要な要素にもなっています。とはいえ、紙の本をそのまま電子化した電子書籍では、単に白紙のページとして表示されるだけです。
リフロー型の電子書籍では、雰囲気をかもしだすというよりは「単に無駄なスペース」にすぎません。
電子書籍のページをめくって白紙だったら、さらにページをめくらなければなりません。余計な手間がかかってしまい――無駄、、、というわけです。
ですから、白紙スペースに特別なこだわりや思い入れがあるのでなければ、ePub ファイルに変換する際に、白紙になっている見返しや遊び紙のページを削除しておく必要があります。
オンデマンド出版の紙の本は、いわゆるソフトカバーと呼ばれるもので、洋書のペーパーバックのような簡易製本になります。日本の製本用語でいうと、並製本の「くるみ」です。
これは、「本文となる中身を一枚の表紙でくるんで糊づけし、上下と小口の三方を裁って仕上げたもの」です(日本エディタースクール編『標準 編集必携』)。この場合、遊び紙を入れる余地はないですね。
というわけで、電子書籍のみの場合でも、それに加えてオンデマンド出版による紙の本を出す場合でも、白紙のページを削除するか残すかのを判断し、それぞれ異なるファイルを用意する必要があるというわけです。
実際には、紙本用に白紙のページを含めたファイルを用意しておいて、電子書籍用にファイル変換する際に、そこから該当部分を削除しておくという手順になるでしょうか。もちろん、その逆でもかまいません。
7. 奥付に必要な項目
奥付は、本の最後(洋書では表紙裏などの冒頭)に、著者や出版社、発行年月日などの書誌情報を記載したものです。
奥付に記載する項目としては、次のようなものがあります。
書名 発行年月日 刷・版 著者、訳者、編者の名前(図書館等でのデータ処理用に可能であれば読み仮名も) 著者等の略歴 発行者名と発行所(住所、電話等) 定価 著作権表示 © ISBN(国際標準図書番号)
※すべてを網羅する必要はなく、自由に取捨選択してかまいませんが、
書名、著者名、発行年月日、発行者
は、最低限、必須でしょうね。 自分のお気に入りの本や出版社の刊行物を参考にするという手もあります。
※奥付の組み方や配置に「ねばならない」はありません。 かつて必須だった「検印」は現在では見かけませんし、また電子書籍であれば、出版者の住所や電話番号よりウェブサイト(URL)やSNSのアカウントの方が読者には便利かもしれません。
8. カラー画像の処理(RGB と CMYK)
電子書籍のみの出版であれば、この項目は読み飛ばしてかまいません。
しかし、紙本の出版も考えているのであれば、ここで述べることは、特に表紙の扱いで重要になってくるので注意してください。
三原色という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
シアン(C、水色)、マゼンタ(M、赤紫色)、イエロー(Y、黄色)という三色の絵の具を、それぞれの割合を変化させてまぜることで、すべての色を作り出すことができます。
いろいろな絵の具の色をまぜていくと、だんだん濁にご濁っていき、最後には黒っぽくなりますよね。完全な黒にはならないため、これに黒(K)そのものを追加し、それらを組み合わせてさまざまな色を作り出せるのですが、これを絵の具や印刷物の三原色(CMYK)と呼びます。
一方、スマホやデジカメで撮った写真やパソコンで描いたイラストなどは、これとは別の「光の三原色」でできています。赤(R)、緑(G)、青(B)の頭文字をとってRGBと呼ばれます。
光の三原色は、絵の具などの三原色と異なり、まぜればまぜるほど白に近づいていきます。
電子書籍に使うカラーの画像は、後者の光の三原色を用いています。
ですから、これを紙にそのまま印刷すると、スマホやパソコンなどの画面で見たものとは少し印象が異なったりします。どちらかというと「くすんだ感じ」になりがちですね。
印刷の現場では、RGBのカラー画像を印刷用のCMYKに変換処理する際に、できるだけ元の色合いを再現できるよう、変換用プロファイル(Japan Color 2011 Coated) なども用意されています。
一般には、この日本標準のプロファイル変換で、ほぼ問題のないレベルに仕上がることが多いと思いますが、写真集や画集など、デザインやイメージに作者や編集者のこだわりがある本では、微妙に異なる色合いや風合いについて、手作業で微調整が必要になったりします。
9. オンデマンド出版(紙の本)と判型
判型とは、要するに、本の大きさ(サイズ)です。
オンデマンド出版の紙の本は、洋書のペーパーバックのイメージです。本文テキストが印刷された薄い用紙の束を、少し厚い紙の表紙(表、背、裏)で包んでいる形です。
文庫本や新書に加えて、単行本は四六判や菊判、B5判、B6判、A5判、A4判などがあり、雑誌を含めればさらに多くなります。
大部数が印刷される大きな出版社の通常本に比べると、読者の注文に応じて一冊ずつ印刷・製本するオンデマンド出版の本はどうしてもページ単価が割高になり、結果として本の価格も高めに設定せざるをえません。
本に限らず、一点物や手作り品は大量生産できないため量産品に比べて割高になるのと同じです。
電子書籍にあわせてオンデマンド出版を考えている場合、紙本の判型を決めておく必要があります。
リフロー型の電子書籍に判型という概念はありませんが、オンデマンド出版では基本的にPDFファイルが基本となるので、判型を決めた上で、フォントの指定、余白の大きさ、複雑なレイアウトなどについても、細かく指定が可能です。そして、それがそのまま本の形になります。
判型によって、文字の大きさや1行の文字数、1ページの行数が変化し、それによって本全体のページ数、ひいては本の価格に影響してきます。
ここでは雑誌などをのぞいた一般的な本について、主な判型のサイズと用途を示しておきましょう。
| 判型 | サイズ | 用途例 |
|---|---|---|
| 文庫(A6判) | 10.5 x 14.8 cm | 文庫本 |
| 新書判 | 10.3 x 18.2 cm | 新書 |
| 四六判 | 12.7 x 18.8 cm | 単行本 |
| B6判 | 12.8 x 18.2 cm | マンガ本 |
| A5判 | 14.8 x 21 cm | 教科書 |
| 菊判 | 15 x 22 cm | 単行本 |
- ※ 同じ判型でも各社で微妙に異なる場合があります。
- ※上のサイズは代表的な例で、オンデマンド出版の会社によって、±数ミリ幅で変化させて指定されることもあります。
10. 国際標準図書番号 ISBNと書籍JANコード
ISBNは国際標準図書番号を示す13桁の番号で、国や地域ごとに刊行物に固有のコードを割り当てるものです。出版された国はどこで、発行者は誰かなどの書誌情報が示されています。
個人が自著の電子書籍を出すだけであれば、ISBNは必須というわけではありません。
日本国内で流通する書籍には、さらに分類や価格情報を加えた「日本図書コード」があり、それを(通常は2段の)バーコードで表したものが書籍JANコードです。
こうしたコードは発行者が勝手につけてよいわけではなく、きちんと登録した上で利用しなければなりません。
次の例はエイティエル出版で発行している『六分儀と天文航法入門』(表紙、左)で、右は裏表紙に印刷されている書籍コードを拡大したものです。

上の2段が書籍JANコードで、その下にISBNコードと本のジャンル、本体価格が示されています。
詳細については、日本図書コード管理センターのウェブサイトを参照してください。このコードを利用する場合の説明と解説が掲載されています。
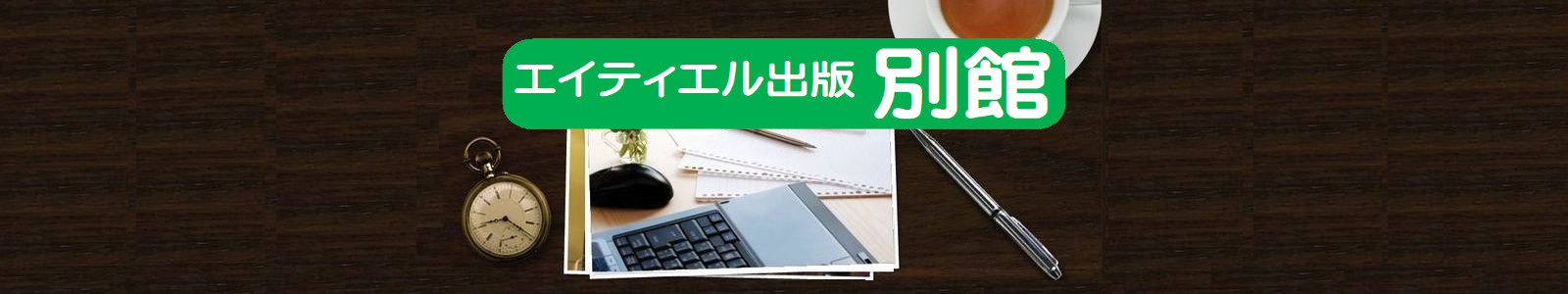
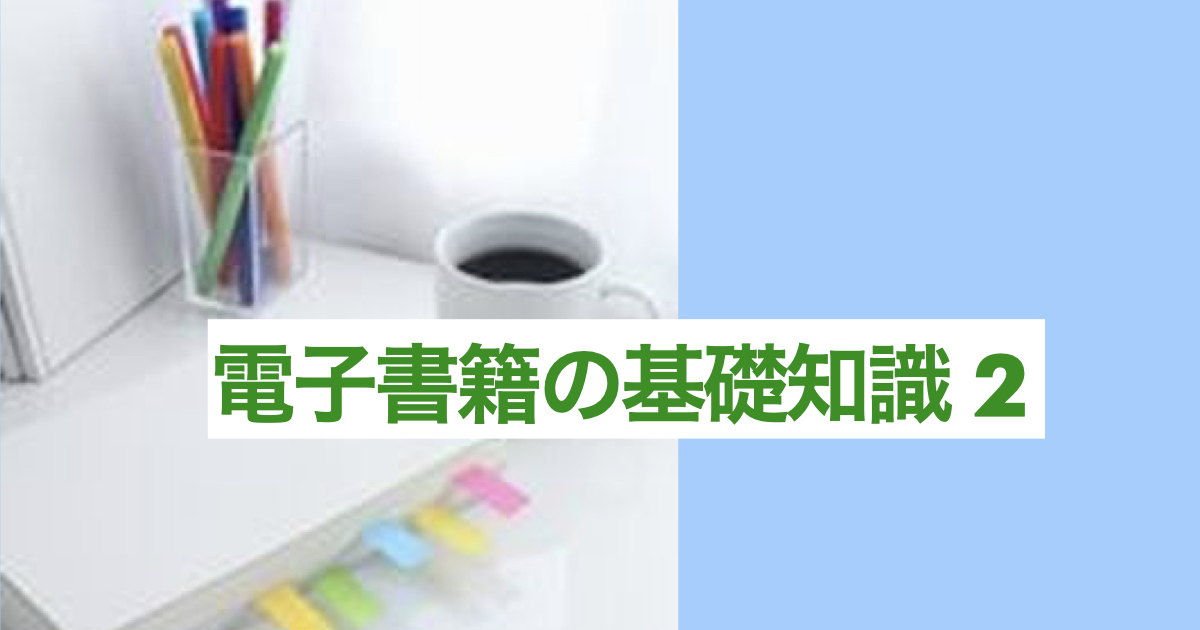


コメント